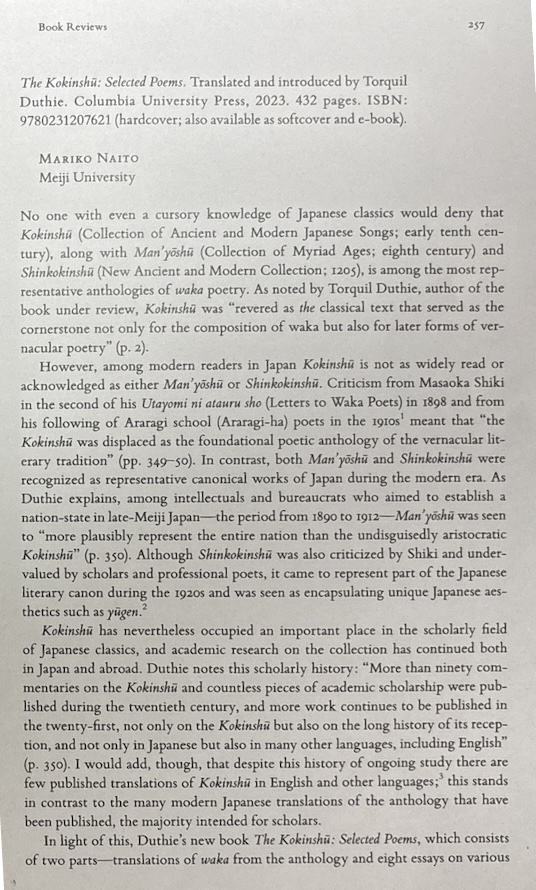2022年から24年に行った調査の結果をもとにした拙稿が刊行されました。
内藤まりこ「ロバート・ヴァン・グーリックのアジアをめぐる複数の思想に関する研究」『明治大学人文科学研究所紀要』第92冊、2025年3月https://meiji.repo.nii.ac.jp/records/2001695
1.研究開始当初の背景
本研究が調査の対象とするロバート・ファン・ヒューリク(Robert Hans van Gulik, 1910-1967)は、欧米圏や中国における東洋研究において無視することのできない研究者である。ファン・ヒューリクは外交官としてアジアを歴任中に中国と日本を中心とする東洋文学や文化に関する膨大な数の一次・二次資料を手に入れ、それらに関する中国語や日本語、英語、オランダ語で数多くの論考を発表していた。また、ファン・ヒューリクは、多くの推理小説作品を著しており、英語及び中国圏においては人気作家としても名が知られる人物である。
このように外交官・東洋文化研究者・推理小説作家という複数の顔を持つファン・ヒューリクの活動の全貌を明らかにしようとする研究は、欧米圏や中国において精力的に行われてきた[i]。直近では2021年4月にオランダ・王立アジア美術協会に於いて、欧米及び中国の研究者達が参加し、ファン・ヒューリクが第二次世界大戦後の東洋史・東洋文化研究のみならず文学や翻訳研究等、数多くの分野に対して果たした多大なる貢献の内実を国際会議が行われたばかりである[ii]。
欧米圏や中国におけるファン・ヒューリクに関する研究動向に比して、日本では現在、いかなる研究分野でもファン・ヒューリクの功績が取り上げられることはほぼない。しかし、ファン・ヒューリクは第二次世界大戦直後に日本に外交官として滞在していた当時(1935-42, 1949-53, 1965-67)、西洋の東洋史家として知識人達の間ではよく知られる存在であった。実際のところ、ファン・ヒューリクは、日本の研究者達の依頼を受けて日本古典文学の成り立ちに関する論考を寄稿したり、座談会に招聘されて西洋の古典と日本の古典とを比較したりする等、日本の知識人と積極的に交わっていた[iii]。こうした活動を通じて、ファン・ヒューリクは、国外の研究者として日本古典の文学的価値を精査し、評価する重要な役割を担っていたと考えられた。
2.研究の目的
本研究の目的は、ロバート・ファン・ヒューリクの著書及び蔵書を編集文献学の手法を用いて調査・分析することで、第二次世界大戦後の日本社会において海外の研究者達が日本古典文学の価値づけや評価にどのように関わっていたのかを明らかにするのと共に、第二次世界大戦後のヨーロッパにおいて日本古典文学がどのように紹介され、いかなる評価を与えられてきたのかを詳らかにすることである。
3.研究成果
調査を進める過程では報告者は自身が想定していたよりも遥かに膨大な量のファン・ヒューリクに関わる資料に出会うこととなった。それらの資料が示していたのは、ファン・ヒューリクが培ったアジアにとどまらぬ世界中の文化や風俗に関する幅広い知識や、そうした文化や風俗の成り立ちと歴史的変遷を掘り下げていく旺盛な探究心であった。そうしたファン・ヒューリクの人間像に近づいていく中で、報告者はファン・ヒューリクの研究活動を〈日本〉という狭き射程から切り取ることに躊躇を覚えるようになった。なぜなら、先行研究において、ファン・ヒューリクの日本研究に対する貢献が触れられてこなかったとはいえ、彼の研究活動を〈日本〉という視点からのみで語ることは、その研究の豊穣さを矮小化することになり、結果としてファン・ヒューリクが当時の日本研究の領域の中では格段に広い射程から〈日本〉を捉えていたことを適切に伝えられない恐れがあると考えたからである。
そこで、報告者は調査活動の方針を一部修正し、本研究において「ファン・ヒューリクはいかにしてアジアへの興味関心を養い、日本を含むアジア地域に対していかなる思想を培ったのか」という問いに取り組むことにした。そして、こうした大きな問いの答えを導き出すために、調査対象をファン・ヒューリクの日本滞在時期に限定せず、ファン・ヒューリクの人生の全体にまで広げ、3つの観点からファン・ヒューリクの思想の包括的に捉えることを試み、以下に述べる成果を得た。
① ファン・ヒューリクの生い立ちにまで遡り、1910年オランダ東部に生まれ、オランダ領東インド(現在のインドネシア)で幼少期を過ごした彼が、いかなる文化的・思想的な生育環境に置かれたことで、日本を含むアジアへの興味関心を育むこととなったのかを検討した。
:1910年にオランダ東部のヘルダーラント州(Gelderland)にある町のズットフェン(Zutphen) に出まれ、3歳の時に父の仕事に伴って住んだオランダ領東インド・ジャワ(Java)のバタヴィア(Batavia, 現インドネシアの首都ジャカルタ)にて11歳にオランダに帰国するまでに彼がいかなる生育環境に置かれたのかを検討する。その結果、ファン・ヒューリクが、ワヤン・クリ(Wayang Kulit) と呼ばれる人形を用いた影芝居などのインドネシアの伝統芸能に心酔していたことや、自宅に出入りするインドネシアの人々と交流を深めたり、現地の中国人街に出入りしたりすることで、アジアの言語や文化に興味を深めていたことを指摘する。以上のことから本章では、ファン・ヒューリクの幼少時代は、植民地政策を掲げるオランダのアジア地域への接近という歴史的背景の下で自身のアジアへの興味関心を養う時期となったことが明らかになった。
② オランダに帰国したファン・ヒューリクがアジアへの探究を研究活動の形で実践することとなったナイメーヘンでのギムナジウム時代(1923-30)、ライデン大学での学部時代(1930-33年)からユトレヒト大学での大学院時代(1933-35年)に博士号を取得するまでを取り上げ、ファン・ヒューリクが置かれていたアジア研究の思想的な環境とはいかなるものであったのかを調査した。
:ファン・ヒューリクの伝記や彼が著した論文を読み解くことでこうした学生時代の足跡を確認し、ファン・ヒューリクの学生時代はアジアの言語と文化への旺盛な探究に費やされたことが分かった。その上で、当時のオランダを含む西洋諸国の大学に設立された東洋学の学問分野がどのような歴史的背景の下で成立し、そこでいかなる研究が行なわれていたのかを調査した。そして、中国学に関しては、16世紀後半に中国にて積極的に行われた宣教師の布教活動がその起源に求められること、そして宣教師たちが現地の知識人たちから学んだ文献学の手法が19世紀以降のヨーロッパの中国学にも引き継がれ、儒教や道教などの古代中国の伝統的思想を解明する研究が行われていたことが明らかになった。さらに、1970年代後半にパレスチナ系アメリカ人の文学研究者エドワード・サイード(Edward Said, 1935-2003 )が指摘する「オリエンタリズム」の議論を参照し、西洋に〈近代〉を、アジアを〈伝統〉を振り分ける二項対立的な思考が、ヨーロッパの中国学の思想の中にも見出されることがわかった。以上のことから本章では、ファン・ヒューリクの学生時代を過ごしたヨーロッパの東洋学には、アジア(東洋)について近代化を果たしたヨーロッパでは失われた伝統がいまだに残されている理想の地と捉え、東洋に対して憧憬の眼差しを向けるというオリエンタリズムが見られること、そうした思想的な環境の中で彼は漢字文化や儒教などの伝統を生み出した中国をアジアの文化的思想的中心地と見做し、そうした伝統を審美的に読み解く探究姿勢を獲得した可能性があることが明らかになった。
③ ファン・ヒューリクは大学院修了後、1935年にオランダ王国の外務省に入省した直後から秘書官として日本に滞在した。その後の何度か数年単位でのオランダやアメリカでの勤務を除くと、1968年9月24日に死去するまでファン・ヒューリクはその人生を外交官としてアジア圏で費やしている。そこで、ファン・ヒューリクが外交官として勤務しながらも執筆した膨大な著作物を読み解くことで、彼が日本を含むアジアに対していかなる思想を培っていたのかを検討した。
:まず、いくつもの文化的領域に活躍の場を持つ一方、政治や経済などの世俗的所業から一定の距離を置こうとするファン・ヒューリクの振る舞いが、中国の伝統的な人間の一類型である「文人」と一致する点が見出された。ファン・ヒューリクは、当時の中国社会において失われつつあった「文人」たる生き方を自らが実践することで、失われた伝統を復興させ、翻って西洋だけでなく東洋を席巻する近代化を批判しようとしていたと考えられるのだ。次に、こうしたファン・ヒューリクの伝統重視・近代批判の思想は、ファン・ヒューリクの日本に関する著作物においても顕著に見られることが明らかになった。ファン・ヒューリクは日本の様々な伝統文化を取り上げて数々の論文を発表しているが、それらはいずれも漢字文化や儒教などの中国の伝統に由来する事象であった。日本が帝国主義を掲げ、中国を植民地化していった時局に記された著作物においても、ファン・ヒューリクは日本社会の文化的深層に中国から脈々と受け継がれた伝統を見出そうとする姿勢を貫いていたのである。
以上の調査分析の結果から、「ロバート・ファン・ヒューリクはいかにしてアジアへの興味関心を養い、日本を含むアジア地域に対していかなる思想を培ったのか」という本研究で取り組んだ論点に対しては次のような結論が導き出されるだろう。すなわち、「ファン・ヒューリクはまず、幼少時代をバタヴィアで過ごした経験からジャワの伝統文化と、その文化の古層に底流する古代インド文化への興味関心を養った。また、祖父の影響から当時のヨーロッパに普及していた古代中国の伝統を理想的な「他者」として捉えるオリエンタリズムの思想を吸収した。次に、学生時代をオランダの教育機関で過ごした経験から古代中国の伝統文化への興味関心を養った。また、当時のヨーロッパの東洋学が、16世紀後半以降に宣教師が中国から持ち帰った文献学的研究手法や中国への認識を継承していたことから、古代中国の道徳的な理想の地として捉える思想を摂取した。さらに、外交官時代には、研究・文化活動に邁進して古代中国の文人の振る舞いを実践することで、失われた古代中国の伝統を発見し、近代社会の価値観を相対的に捉えようとした。さらに、「東洋」を一枚岩としては捉えず、中国とインドがそれぞれ別の中心となり、日本やジャワが周縁に位置付けられる複数の文化圏が折り重なる地域として捉える思想を培った」というものである。
4. 今後の課題
今回の研究の限界を2点指摘し、今後の課題としたい。
まず、ファン・ヒューリクの人生の軌跡を辿る際に、その細部の情報をファン・ヒューリクの伝記的研究に頼ることが多く、それらの研究が依拠している一次資料に当たることができなかった点が挙げられる。本研究に取り組んだ2年間ではファン・ヒューリクに関する資料を所蔵しているオランダのライデン大学図書館、オランダ王立アジア美術協会、ボストン大学図書館において、手紙や創作ノート、草稿等の一次資料は確認できたが、先行研究が参照しているはずの日記類を見つけることができなかった。しかし、最新の情報によると、ライデン大学図書館に直筆の日記が寄贈されたとのことであるので、早急に確認して本稿の議論の妥当性を検討したい。
次に、本研究の調査を通じて、ファン・ヒューリクが日本滞在中に交流を深めた数多くの知識人や文化人達との間でやりとりした書簡を多数発見した。中でも江戸川乱歩らの作家達とはファン・ヒューリクが日本を離れてからも頻繁に書簡のやり取りをしていたことがわかったが、本研究の期間内には発表する機会がなかった。そこで、2025年度にはファン・ヒューリクがいかなる知識人や文化人のコミュニティを築いていたのか、また、日本文学の文壇にいかなる寄与をしたのかを詳述する論文を発表していきたいと考えている。
[i]. Janwillem van de Wetering, Robert van Gulik: Zijn Leven Zijn Werk. Amsterdam: Loeb, 1989., C.D.Barkman, Een man van drie levens: biografie van diplomat, schrijver, geleerde Robert van Gulik. Amsterdam: Forum,1993., Herbert, Rosemary, “Van Gulik, Robert H(ans)”, in Herbert, The Oxford Companion to Crime and Mystery Writing. Oxford, Oxford University Press, 1999等が代表的な先行研究。
[ii]. The KVVAK Van Gulik 2-day event, https://www.kvvak.nl/agenda/2021/the-kvvak-van-gulik-2-day-event/(閲覧年月日:2021年9月6日)
[iii].ヴァン・グーリク「源氏物語を讀んで」『望郷』第八号、一九四九年六月、ヴァン・グーリク、フランク・ホーレー、石田幹之助、魚返善雄「東洋文化を探る座談会」『読売評論』第二巻第四号 一九五〇年四月